みんなに声を大にして言いたいことがある。
全員、契約内容に疎すぎる。
巷には正しいことであるかのように、契約を度外視した事項が多すぎる。その典型が、会社の雇用契約である。
では、先ずあなたの会社入社時の判断基準を教えてもらいたい。
- 働きやすい環境
- 早い段階で昇給・昇進
- 福利厚生、その他支給制度の充実
- 実力主義
大方このような内容だろう。さて、ではその「根拠」を提示してもらいたい。何を「根拠」にしてどう判断しているのか?Webサイトで、面接時の口頭で、あるいは友達から、、、すべて「根拠」とはならないことに気づいてもらいたい。
今後の情勢的には「実力主義」を採用する会社が増えてくる。
現状、会社が実力主義である「根拠」は、実際にその会社で働くこと以外で確認できない。そして、ほとんどの会社が「就業規則」で、年功序列を謳っているわけである。実際、この矛盾は大企業にすら見られる。また、本来これらの「矛盾」は「違法」であるのだが、労働者が総じて甘んじているのが現状である。
じゃあ、こういう矛盾を事前に一瞬で解決するにはどうすれば良いか?
それこそが「就業規則」であって、あらゆる不明点は「就業規則」を見ればすべてが記載されている。なぜ、そう言えるのか?
就業規則とは|労働基準法89条
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項(総じて「働き方」に関する事項。)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業規則は、労働基準法に基づき「作成」が義務付けられる法的書面である。
決して難しい話をしたい訳ではなく、就業規則にはあなたが「不明瞭」だと思われる事柄について「網羅的」に記載されているのである。至れり尽くせりの書面なのである。しかも、これが法的に保障しているため、その内容につき「嘘偽りない」と断言できるわけである。
例えば、
面接か何かで「活躍次第で30歳で部長職、年収⚫円になれる」と言われたとする
その根拠とするには、その会社の就業規則を見て、30歳で「部長職」に昇進、昇格する制度があるかどうか確認すれば良い。当たり前だが、そんな制度を設けている会社は「ない」のであるが。
これが分かると、働く側、会社側双方に多大な「利益」となる。
採用のミスマッチ、時間が無駄にならないからだ。
入社後に疑心暗鬼になりながら、石橋を叩きながら相手の嘘を勘ぐっていた手間を省くことができる。相手会社からすれば大っぴらに「嘘をつく人間」が会社の窓口であるのが分かるため、そんな会社は「入社しない方が良い(即回避)」と判断できる。
現行法では、就業規則を「入社前」に活用できない|労働基準法106条1項
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
上記は、就業規則の「周知義務」に関する根拠規定である。
あ、周知義務あるじゃん。なら良いじゃん。ではない。
要約すると、就業規則は「労働者」に周知する、と規定される
この労働者は、就業規則を閲覧できる者は企業に入社が決まった者と解される。すなわち、この労働者に「第三者」は含まれないと解されている。
どういうことか?
入社意思がある人物がいたとして、現行法では入社前の「就業規則」の閲覧は不可能となっている。
僕は「労働基準法106条1項」を法改正すべきだと主張する。
その請願・陳情書・意見書の手続き
さて、以上の主張をまとめると「現行法」では不可能であるので
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm
と言いつつ、実のところ法改正は「不要」である
「就業規則」の任意開示は、企業の差別化に繋がるため
現状「就業規則」の開示は「任意」であるので、むしろそのままの方が好都合であるかも知れない。なぜなら、「就業規則」を開示するかどうかで企業の差別化に繋がるからだ。
具体的に言えば
就業規則を外部に公開できない会社があったとして、「就業規則」すら見せれない会社と言う事ができるからだ。就業規則は第三者に開示義務がないだけで、入社すれば誰でも請求閲覧できるものであるから。はっきり言って開示しない理由が分からない。なのでこの場合、疑わしき者は罰する理論で、応募者は即回避した方が良いと判断できる。
一方、就業規則
「根拠」を請求できない会社環境こそ問題
先ず抑えておきたいのは、結局正当な主張には必ず「根拠」が必要である。
不動産取引で言えば、権利証であったり「登記」がそれに当たる。
一方、会社では「根拠」を請求できない場合が多い。
面白いことに理系で最も論理的な人間が在籍する「技術系」の会社に多い。なぜかと言うと、技術的な根拠が総じて法的根拠に基づかないからだ。理系の技術系ほど「根拠」を無視して取り組んでいる。理系は論理的で賢いと思われがちだが、その真逆で理系職種ほど「根拠」を度外視した職種はない。
理系技術職は根拠が法律に基づかない
本来、誰よりも論理的に思考できる理系であるはずが、他のどの職種よりも「非論理的」となるのが理系技術職である。その醜悪の根源は、一言で言えば低俗な人間が幅を効かせやすいことだ。
- 決めれない、決まっていないので誰も正否を判断できない
- 法律に類する法的効力を有する技術がない
- 総じて「年功序列」が法に類する根拠とされ、防御、弁解、抗弁の機会に乏しくなる
僕が技術職であった頃「あーこの職業駄目だな。」と一瞬で見限った経験がある。
僕がプログラムを納品したとき、非IT系の何の専門性もない人間から、プログラムの「命名規則」をきちんとしろと言われた時だった。かなり頭に来たが、なぜならこの議論に明確な回答はないからだ。それこそ、法律のように「何をどのように定めれば良いか」なんてどこにも記載されておらず、どんな記載でも許されるのが「命名規則」であり、例えば、inputfileを、inputFile(キャメル記法)、input_fileなど緩い記述法があるに過ぎない。
そういったことを、「年功序列」で保護された上司と部下の関係で議論しても極めて不毛だと感じた。
これは一例でしかなく、僕が知る限り技術職で「根拠」を明確にした記憶は皆無である。根拠がない場合、概ね「治外法権」となる。「声のデカい人」「年功序列の恩恵を受ける人」などが根拠となり、自分で判断できない訳である。例えば「あの人がこう言ったから」が常套句となる。
- 偉そうに聞こえる
- 言えば、関係がギクシャクする
- 言いづらい
中には、根拠は?
と言われて、あいつ偉そうに俺に根拠を求めてきやがった。とか言う人がいる。甚だ低俗である。
根拠は議論の基礎であり、根拠を求められて「カチン」ときたなど幼稚なことこの上ない。中には、根拠を提示するのも時間を要する。と言う人がいるが、これも間違いである。根拠は常日頃から即提示が原則だからである。
それでも、根拠は?と言われて、苛つく場合もある。あえて根拠に乗じた遅延行為などがそれに当たる。こういう場合は、僕は、これを読めクソ野郎と「記載の通りだ」とPDFを投げつける。そういうやり取りも三回限りで、三回以上やってくるやつにキレる。

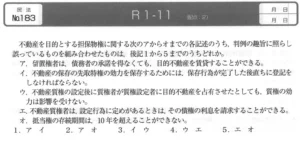





コメント